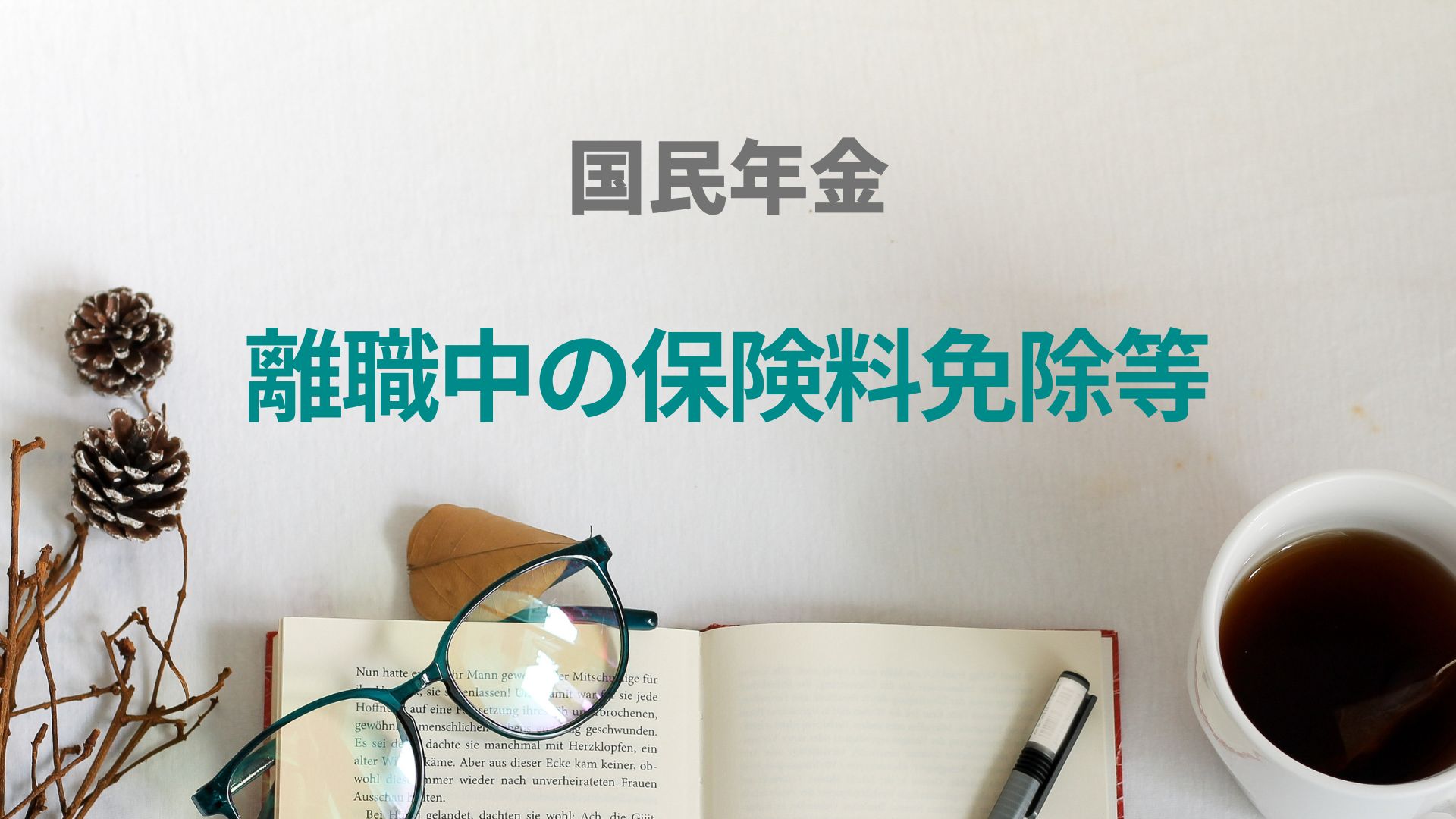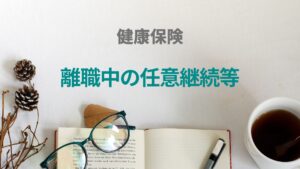会社を辞めた後の国民年金について、基本的なところから必要な手続きまでを纏めました。
私自身、今回は退職後に離職期間があったので、実体験も踏まえた上で記載しています。退職から次の会社への入社まで期間が空く方は、国民年金をしっかり納めるのか、申請して免除するのか等、対応の参考になればと思います。未納になってしまわないように気を付けましょう。
国民年金の基本
国民年金の加入は必須
日本年金機構のホームページに以下のような記載があります。
わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といいます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得に対応していくことが可能になっています。
上記のように国民年金は、20歳以上60歳未満の全ての国民の加入が必須となっています。
国民年金の分類
国民年金の加入者は以下のように分けられます。
- 第1号被保険者:第2号、第3号以外の人(自営業者、学生、無職等)
- 第2号被保険者:会社員、公務員(厚生年金加入者)
- 第3号被保険者:第2号に扶養されている配偶者
会社員は第2号
会社員の場合は、基本的に厚生年金に加入していて、保険料は会社側が納めているので、あまり意識していない方もいるかと思います。保険料率は18.3%で、これを労使折半しています。現在の上限は、標準報酬月額が65万円以上で、会社員側の負担額が月額59,475円となっていますが、段階的に現状が引き上げられることが決まっています。
国民年金の保険料
保険料は現在、月額17,510円です。減額される年もありますが、ほぼ毎年少しずつ負担額が増えています。
対象月の分を、翌月末日までに支払う必要があります。当月末の口座振替にしたり、前納(半年分、1年分、2年分)にしたりすると、若干ですが保険料が割引されます。支払いが遅れた場合でも、2年以内(免除や猶予を受けた場合は10年以内)の追納が可能です。
保険料の免除も可能
年収が一定額以下の場合や失業した場合等、納付が困難とされる場合は、保険料の免除が可能です。免除額は、全額、3/4、半額、1/4の4パターン存在します。免除期間中は未納扱いにはならず、年金受給時も全額納付した場合の半分の額を受け取ることができます。(免除分は半分納めたような扱いとなる)
国民年金の受給
20歳から60歳になるまでの40年間全額を納めた場合、年間831,700円の老齢基礎年金を受給できます。
支給日は、偶数月の15日で、前月までの2ヶ月が振り込まれます。未納や免除の期間がある場合は、上記の金額からその分が差し引かれた額となります。厚生年金は国民年金も含んでいるので、60歳まで会社員として働いた方は、老齢基礎年金も全額受給できます。
国民年金には、老齢基礎年金の他に障害基礎年金と遺族基礎年金があります。また、会社員だった方は、厚生年金として、加入期間と当時の収入に応じて老齢厚生年金も受給できます。本記事では、退職後、離職中の国民年金がテーマなので、この辺りの内容は省きたいと思います。
国民年金の基本の纏め
・20歳以上60歳未満は加入必須
・保険料は17,510円/月
・失業時は保険料の免除が可能
退職後の対応
ここからは、退職後に対応すべきことを記載していきます。
退職後は第1号か第3号に
間を空けずに次の会社に転職する場合は、転職先の会社側が厚生年金の手続きをしてくれますが、離職期間ができる場合は、国民年金への加入手続きを自身で行う必要があります。個人事業主になる場合も同様に国民年金への加入が必要です。
以降は、基本的に第1号被保険者(自営業や無職等)になる場合についての記載となります。第3号被保険者になる、つまり配偶者の扶養に入る場合は、配偶者側の会社への届出が必要となります。
必要書類
手続きには、以下の書類を用意する必要があります。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
- 退職日のわかるもの(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等)
離職票の要求を忘れずに
本人確認書類は問題ないでしょうし、年金番号の書類も探せば見つかるかと思います。離職票については、元の勤務先に発行してもらう必要があるので、退職する際にしっかり要求しておきましょう。
離職票が届かないと国民年金の手続きだけでなく、ハローワーク(公共職業安定所)での手続きも進まなくなってしまいます。ハローワークでの手続きが遅れると、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給開始時期も遅れてしまいます。会社側がちゃんとやってくれるだろうと考えず、明確に発行を要求しておくことを個人的にはオススメします。もし退職日から2週間くらい経っても届かない場合は、会社側に問い合わせてみた方が良いと思います。
保険料を納付する場合
国民年金被保険者関係届出(申請書)を市区町村の担当窓口に提出します。電子申請も可能となっています。上述の必要書類が用意できていれば、あとは各自治体のホームページ等を確認しながら進めれば問題ないと思います。
申請書を提出後、1ヶ月程度で国民年金保険料納付書が送られてくるはずですので、それに従い保険料を納付します。
保険料を免除する場合
国民年金の保険料のところで記載しましたが、失業した場合は保険料免除の対象となります。失業等による特例免除として、申請すれば基本的に全額免除で承認されるかと思います。免除することにより以下のようなメリットがあります。
- 離職期間中の支出の削減
- 全額納付した場合の半額分の年金額を受給可能
- 追納も可能(10年以内)
免除申請せずに未納のままにしていた場合、当然その期間の分は年金受給額から引かれてしまいます。免除することで半額納めたような扱いになりますし、追納の期間も2年以内から10年以内に延びます。納付すべきか悩んだ場合は、ひとまず免除申請をしておく方が良いかと思います。
申請方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を市区町村の担当窓口に提出します。電子申請も可能となっています。詳細については、日本年金機構または各自治体のホームページ等を参照して頂ければと思います。年金手帳と離職票のコピーを用意しておくとスムーズかと思います。
審査期間は2~3ヶ月程度とされているようですが、それより早く結果が来ることもあるようです。失業による申請であれば、問題なく承認されるかと思いますので、気長に結果を待つのみです。仮に審査中に国民年金保険料納付書が届いても納付する必要はなく、免除申請が承認されれば対象期間分はしっかりと免除扱いとなります。
免除期間が過ぎたら再申請が必要
免除期間が終了すると国民年金保険料納付書が届きます。その際も失業状態が続いていれば、再度申請することで全額免除が可能となります。初回の申請時に期間を確認しておき、期間終了後の再申請を忘れないように気を付けましょう。
手続き時期
退職日の翌日から14日以内の対応とされています。
ただあくまでも原則であって、14日を過ぎても手続きは可能です。仮に支払いが遅れても2年以内に追納すれば特にペナルティはありませんし、免除についても申請が通れば過去の分も含めて適用してくれます。
手続きに必要な離職票等を受領してからの対応とするのが良いと思います。私は退職した会社から離職票がなかなか届かず、退職日から1ヶ月以上経ってから手続きをしましたが、特に問題なく対応できました。
国民年金手続き纏め
・勤務先から離職票を受領
【保険料納付の場合】
・国民年金被保険者関係届出を市区町村の担当窓口に提出
・国民年金保険料納付書に従い納付
【保険料免除の場合】
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書を市区町村の担当窓口に提出
・免除期間が終了したら再度申請
【第3号被保険者になる場合】
・配偶者側の会社で手続き
将来の年金が多少減っても現在の支出を減らしたいのあれば免除申請、年金をできるだけ多く受給したいのであれば納付、配偶者の扶養に入れるなら第3号に、といったところでしょうか。免除しても半分納めたような扱いになるので、未納のまま放置だけは避けることをオススメします。
再就職時の対応
国民年金から厚生年金への切り替えは就職先の会社側が対応します。
個人で対応することは特にないですが、年金番号が必要となるので、就職先から提出を求められたらすぐ用意できるようにしておくくらいかと思います。国民年金を払い過ぎていた場合でも、ちゃんと後から還付があるようなので、前納していたとしても心配の必要はなさそうです。
あとがき
会社勤めを続けているとあまり意識しない内容だったかと思います。60歳より前に退職する方、転職時に離職期間ができる方は免除のあたりは知っておいて損はないかなということで、自身の経験も踏まえ共有兼備忘録として記事を作成しました。そもそも将来の年金が不安という方もいるかもしれませんが、未納のままにするよりは免除にしておいた方が無難ではあると思います。
また、年金以外にも退職時に必要な、健康保険の選択、住民税の支払い、失業手当の受領等についても、セミリタイアシリーズとして別途纏めておければと考えています。
最後に、国民年金の手続きは大事なことです。この記事の内容により何か不利益を被っても管理人は責任を負えません。あくまでも参考情報として、ご自身の判断で対応をお願いします。