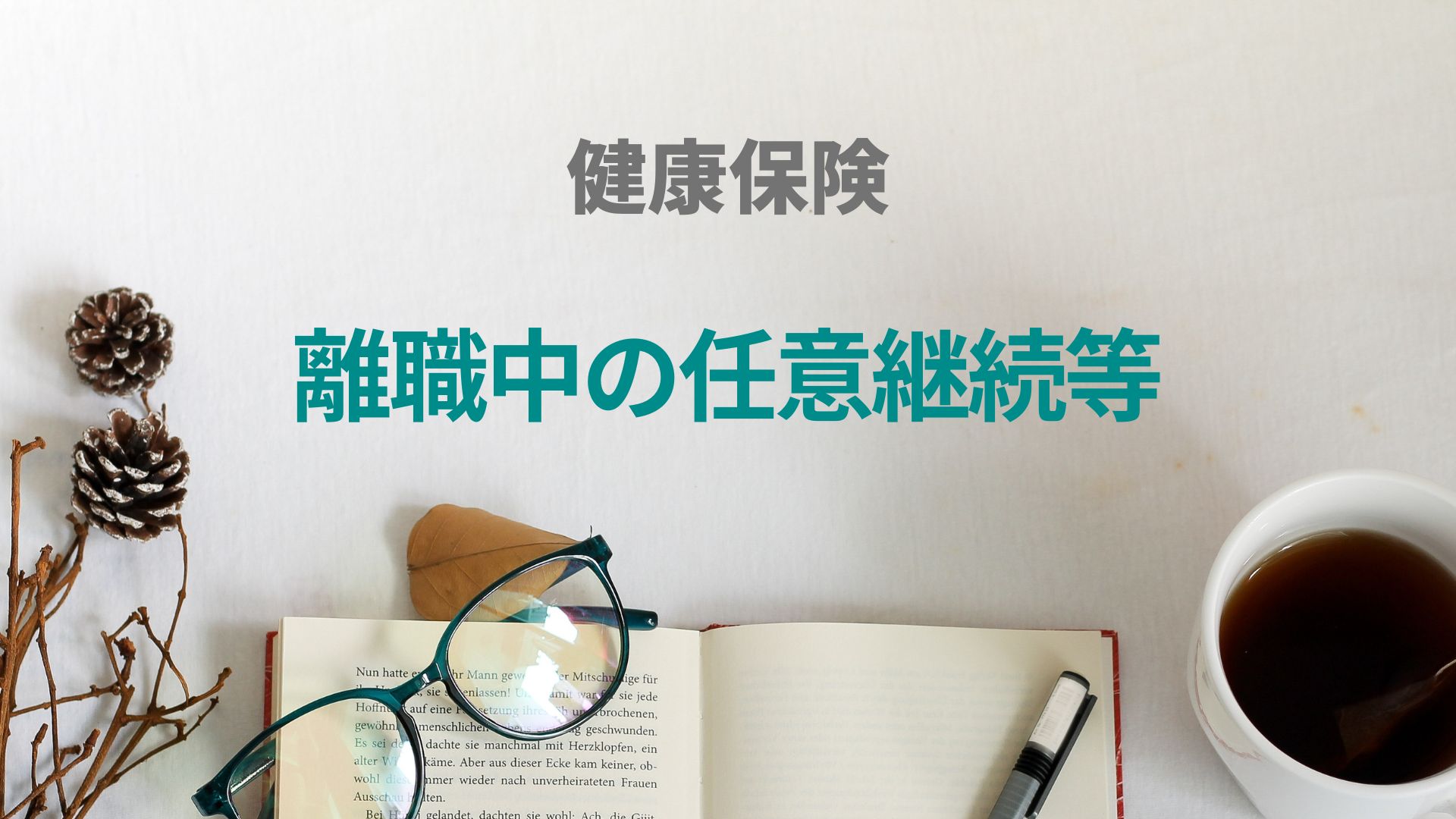会社を辞めた後の健康保険について、基本的なところから必要な手続きまでを纏めました。
私自身、今回は退職後に離職期間があったので、実体験も踏まえた上で記載しています。退職から次の会社への入社まで期間が空く方は、健康保険の任意継続をするのか、国民健康保険に移行するのか等、対応の参考になればと思います。
健康保険の基本
公的医療保険の加入は必須
日本では、国民皆保険制度が採用されているため、何かしらの公的医療保険への加入が義務付けられています。退職後に対応を怠り、医療費10割負担となってしまわないように気を付けましょう。
公的医療保険の分類
公的医療保険は以下のように分けられます。
- 国民健康保険:自営業者、学生、無職等
- 被用者保険
- 健康保険:民間企業の役員及び従業員とその扶養家族
- 共済制度:公務員や教職員等とその扶養家族 - 後期高齢者医療制度:75歳以上
基本的に75歳までは、国民健康保険か被用者保険のどちらかに加入、75歳以降は後期高齢者医療制度に加入となります。
40歳以上は介護保険も
公的医療保険の他に、公的介護保険も存在します。40歳以上になると第2号被保険者として、公的医療保険に上乗せする形で保険料が徴収されるようになります。会社員の方は、給与明細を確認するといつの間にか天引き項目が増えていると思います。65歳以上になると第1号被保険者となり、保険料は基本的に年金から天引きとなります。
健康保険
会社員の場合は、基本的に健康保険に加入しています。健康保険は、以下のように分けられます。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):主に中小企業が加入
- 健康保険組合(組合健保):主に大企業が加入
協会けんぽの加入者数は、約4,000万人で組合健保より多数派となります。保険料率は都道府県により異なりますが、基本的に標準報酬月額の10%前後で、これを労使折半で負担します。
組合健保の方が有利
組合健保は、一定の規模の企業または企業グループが厚生労働省の認可を受けて設立した健康保険組合です。保険料率は組合によって異なりますが、平均すると9%程度と協会けんぽより低い傾向で、保険料負担も会社側の負担率の方が高いケースもあります。保険内容も充実していることが多いため、協会けんぽより有利だと言えると思います。
私は退職するまであまり意識していませんでしたが、厚生年金と違って健康保険は企業によっても差があるので、余計にわかりづらく複雑ですね。会社勤めだと特に気にしなくても問題はありませんが。
退職後も任意継続が可能
健康保険には、任意継続被保険者制度があり、退職後も申請すれば最長2年までは退職前の健康保険を継続することができます。継続の条件として、2ヶ月以上の被保険者期間は必要となります。また、保険料の会社負担がなくなり、個人での全額負担となってしまいます。
国民健康保険
自営業者や無職の方、健康保険の扶養家族ではない方、または健康保険の任意継続中でない方は、基本的に国民健康保険に加入となります。国民健康保険は以下のように分けられます。
- 市区町村国民健康保険(地域保険):主に自営業者や無職の方が加入
- 国民健康保険組合(国保組合):業種や職種毎に個人事業主が加入
国保組合は、医師や弁護士、建設業等、同種同業の従事者が集まって組織されています。保険料が定額となっていることが多く、所得が高い程メリットとなるケースが多いようです。個人事業主として職を持つ場合は、対象となる職種の国保組合を調べてみるのが良いと思います。
離職中は地域保険
離職中の方は、健康保険の任意継続をしない場合、基本的に地域毎の国民健康保険への加入となると思います。保険料は、所得及び自治体により異なります。協会けんぽの保険料率は都道府県別で異なるもののあまり差は大きくないですが、地域保険の保険料率は市区町村によってかなり差があるので、お住まいの自治体のホームページ等で調べて把握しておく必要があります。
保険給付
健康保険の給付には、療養の給付(70歳未満で原則医療費3割負担等)、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金等があります。
医療費関連の基本的な給付は、健康保険でも国民健康保険でも同様となります。ただし、怪我や病気で仕事を休んだ際に給付される傷病手当金、出産のために仕事を休んだ際に給付される出産手当金については、国民健康保険及び健康保険の任意継続では給付対象外となっています。
健康保険の基本の纏め
・会社員は健康保険に加入
・保険料率は10%前後で労使折半
・退職後も2年までは任意継続が可能
退職後の対応
ここからは、退職後に対応すべきことを記載していきます。
早期退職時は以下のいずれかの流れになることが多いと思います。
- 再就職する場合
- 健康保険(退職前) → 任意継続(最長2年) → 健康保険(再就職時)
- 健康保険(退職前) → 任意継続 → 国民健康保険 → 健康保険(再就職時)
- 健康保険(退職前) → 国民健康保険 → 健康保険(再就職時) - そのままリタイアの場合
- 健康保険(退職前) → 任意継続(最長2年) → 国民健康保険
- 健康保険(退職前) → 国民健康保険
退職後の選択肢は3つ
間を空けずに次の会社に転職する場合は、転職先の会社側が健康保険の手続きをしてくれますが、離職期間ができる場合は、以下の3つのいずれかを選択して対応する必要があります。
- 健康保険の任意継続
- 国民健康保険へ加入
- 家族の健康保険(被扶養者になる)
以降は、健康保険の任意継続と国民健康保険への加入について記載していきます。家族の扶養に入り家族の健康保険に加入する場合は、ご家族の勤務先に必要事項を確認の上、対応を進めることになります。
なお、健康保険の任意継続は扶養家族をそのまま継続して加入させることも可能ですが、国民健康保険は扶養という考え方はなく、家族それぞれが加入する必要があります。
健康保険の任意継続
健康保険の基本でも記載しましたが、退職後も退職前の会社の健康保険に最長で2年加入できる制度があります。
保険料が労使折半ではなくなりますが、国民健康保険の保険料と比較して安ければ一旦は任意継続が良いと思います。特に組合健保の方は保険給付の内容が充実していたり、保険料も在職時のそのまま倍になるわけではないケースもありますので、退職時に確認しておきましょう。
必要書類
・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・退職日が確認できる書類(退職証明書等)
※こちらはなくても申請可能
退職時に人事担当等から案内があるとは思いますが、協会けんぽの方は全国健康保険協会のホームページ等を確認、組合健保の方は対象の組合健保のホームページ等を確認して頂ければと思います。離職期間なしで転職すると思われていると案内されないかもですので、人事担当等に任意継続の可能性があると伝えておくと良いと思います。
私は組合健保でしたが、退職時に人事担当の方から任意継続の意思を確認されました。組合健保は企業と紐付いているので案内されやすい気がしますが、協会けんぽの方は自身で勝手に進めてねのケースもあるのかもしれません。
手続き時期
退職の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。
あまり期間に余裕がないので、退職が決まったら意識して対応を進めることをオススメします。
国民健康保険への切り替え
任意継続は最長2年なので、それまでに再就職して健康保険に加入するか、国民健康保険に切り替える必要があります。また、退職後すぐは前年の所得が高く任意継続の方が保険料が少なかったけど、所得が減ったことにより途中で国民健康保険に切り替えた方が保険料が安くなる場合もあります。
退職前の会社員としての所得が高めで、退職後に所得が大きく減少する方は、退職直後は任意継続で所得減少により国民健康保険の保険料が下がったら切り替えるパターンが最適となる可能性が高いと思います。年収、保険者、居住地、世帯構成等に依存するので、もちろん一概には言えませんが。
国民健康保険への加入
離職中に健康保険の任意継続をしない場合は、地域毎の国民健康保険への加入となります。
保険料は、世帯毎に、前年の所得、加入者数、年齢等を基に計算されます。自治体によって保険料率も異なるので、お住まいの市区町村のホームページ(国民健康保険窓口)等で確認が必要です。ご自身で試算するか、窓口に問い合わせせれば算出してもらえるかと思います。
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 健康保険脱退を証明するもの(健康保険資格喪失証明書、離職票等)
基本的には上記のものを用意して、窓口か郵送、オンラインでの申請になるかと思います。詳しくは、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認頂ければと思います。
手続き時期
退職の翌日から14日以内の手続きとされています。こちらは遅れても対応自体は可能です。どちらにしても保険料は退職日翌日分から支払う必要があるので、できるだけ期限内に対応してしまいましょう。
保険料の減免
会社都合退職(倒産、解雇等)や一部の自己都合退職の方は、申請することで保険料を軽減することができます。前年の所得を30/100(3割)として算定されるため、対象となる方は大幅に保険料を下げることが可能です。
もし対象となる方はお住まいの市区町村のホームページ等で確認の上、手続きを進めて頂ければと思います。
退職後の対応の纏め
【任意継続の場合】
・退職日から20日以内に手続き
・基本的に退職手続きの流れで対応可能
・最長2年(切り替えはいつでもOK)
・扶養家族も継続可能
【国民健康保険の場合】
・退職日から原則14日以内に手続き
・自身で市区町村の窓口へ申請
・所得が減れば保険料も減る
・会社都合退職の場合は減額が可能
【家族の健康保険の場合】
・被保険者側の会社で手続き
個人的には保険料負担額が一番少なく済むものを選択するのが良いと思います。どの保険かによって医療費の負担額が変わるわけではないですし。退職前にお住まいの地域の国民健康保険の保険料を調べておき、任意継続とどちらが安いかを比較して判断できるようにしておくことをオススメします。
また、国民健康保険は前年の所得によって保険料が変わるので、離職期間が長くなる場合は、所得が減った状態で計算し直して、任意継続から国民健康保険に切り替える等の対応も考えておく必要があります。
再就職時の対応
健康保険への加入については、再就職先の会社が行ってくれます。会社側の指示従い対応しましょう。
脱退は自身で対応が必要
任意継続していた健康保険や国民健康保険の脱退については、自身で対応する必要があります。面倒かもしれませんが、脱退の対応をしておかないと二重で保険料が請求されてしまいます。保険料を前納していた場合等、払い過ぎた分は返金されますが、返金の計算にも脱退の手続きが必要です。離職期間がある転職時は、確実に脱退の手続きを実施しましょう。
2年の継続期間満了時に限っては、特に手続きの必要はなく、加入団体から任意継続被保険者資格喪失通知書が送付されることになるかと思います。
任意継続の資格喪失
加入している健康保険(協会けんぽまたは組合健保)に従っての対応となります。
必要書類
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 健康保険加入を証明するもの(新たな健康保険証、資格確認書等)
- 資格確認書(返却用、自身で破棄の場合も)
組合健保によっては少し名称が異なったりするかもですが、基本的には上記のものを用意しておけば、対応可能かと思います。詳しくは、加入している健康保険のホームページ等でご確認頂ければと思います。
手続き時期
新たな健康保険の資格を取得後(入社後)、速やかに対応とされています。協会けんぽといくつかの組合健保のホームページを確認してみましたが、具体的な期日は定められていませんでした。忘れないうちに、なるはやで対応しておくのが良さそうです。
なお、新たな健康保険への加入ではなく、申出により任意継続健康保険の資格を喪失する場合は、喪失希望月の前月中とされています。2年経たずに国民健康保険に移行する場合は、こちらの対応になるかと思います。
国民健康保険の脱退
お住まいの市区町村に従っての対応となります。
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 健康保険加入を証明するもの(新たな健康保険証、資格確認書等)
- 国民健康保険の保険証(返却用、自身で破棄の場合も)
基本的には上記のものを用意して、窓口か郵送、オンラインでの申請になるかと思います。詳しくは、お住まいの市区町村のホームページ等でご確認頂ければと思います。
手続き時期
健康保険の資格取得日(入社日)から14日以内とされています。
再就職時の対応の纏め
・健康保険への加入は再就職先の会社が対応
・離職中の保険の脱退は自身で実施
【任意継続の場合】
・再就職後速やかに手続き
・国民健康保険へ移行の場合は前月に手続き
【国民健康保険の場合】
・入社日から14日以内に手続き
あとがき
退職する際にも調べましたが、改めて健康保険は複雑ですね。保険料も高く、自己都合退職でそれなりの年収で全額負担となると退職後の支出にも大きく影響します。しっかり保険料を試算して、任意継続か国民健康保険か、途中で切り替えるのかを選択しないと無駄に多く保険料を支払うことになってしまいますので、知識を付けておきたいところです。面倒ですが、年間で数十万円は変わってくるケースも多いと思いますので、手間をかける価値はあると思います。
国民年金も失業状態の時は免除できたりと退職後の負担を減らすことが可能です。健康保険と国民健康保険に比べれば年金の方がまだシンプルです。
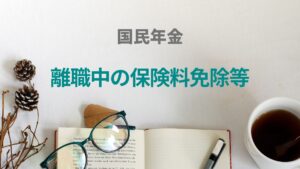
最後に、健康保険の手続きは大事なことです。この記事の内容により何か不利益を被っても管理人は責任を負えません。あくまでも参考情報として、ご自身の判断で対応をお願いします。