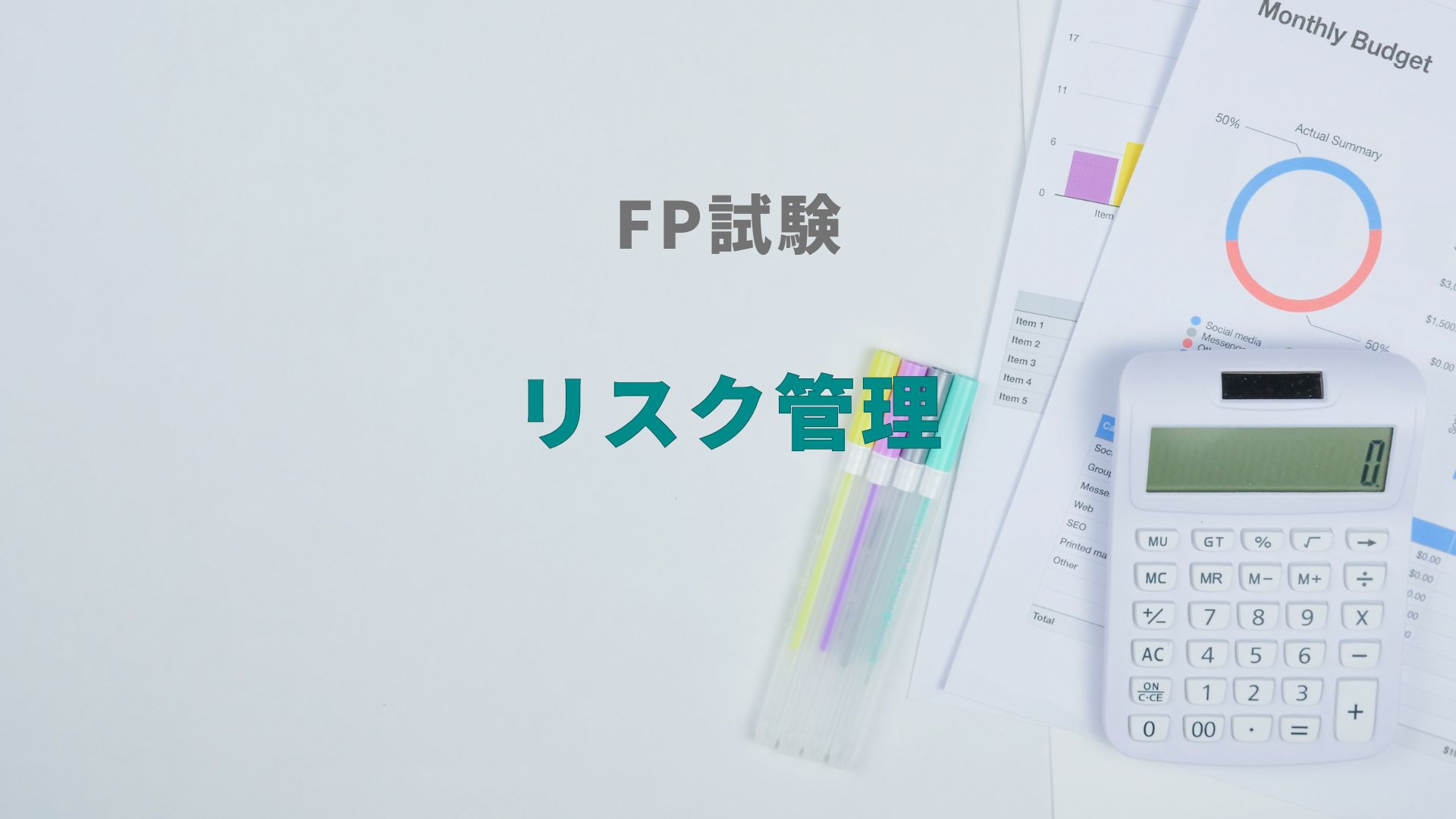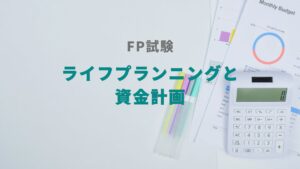FP勉強ノート。
B リスク管理
試験範囲
- リスクマネジメント
- 保険制度全般
- 生命保険
- 損害保険
- 第三分野の保険
- リスク管理と保険
- リスク管理の最新の動向
保険全体
▫️保険の原則
大数の法則:大きな数だと法則性が出る
収支相等の原則:保険料+運用収益=保険金+経費
給付・反対給付均等の原則:事故発生リスクに見合った保険料と保険金とする(損害保険)
利得禁止の原則:保険金受取により儲けることを禁止(損害保険)
▫️契約者等の保護
生命保険契約者保護機構:破綻時の責任準備金の90%まで補償
損害保険契約者保護機構:
自賠責保険/地震保険:保険金の100%まで補償
自動車保険/火災保険:破綻後3ヶ月間は100%、それ以降は80%
疾病/傷害保険:90%
※生保/損保会社は加入義務あり。少額短期保険業者と共済は加入対象外
少額短期保険業者:保険金額/人が1,000万円以内。保険期間1年以内(損害保険は2年)
クーリングオフ:申込日か書面受領日の遅い日から8日以内に書面やメールで契約解除可能
※保険期間が1年以内、営業所に出向いての契約、医師の診査を受けた場合は不可
ソルベンシー・マージン比率:200%以下で金融庁の早期是正措置対象
生命保険
生命保険の分類。
生命保険
- 死亡保険
→ 定期保険
→ 終身保険
- 生存保険
→ 個人年金保険
- 生死混合保険
→ 養老保険
▫️保険料
予定死亡率、予定利率、予定事業費率で算定。
純保険料(死亡保険料、生存保険料):予定死亡率と予定利率を適用
付加保険料:予定事業率を適用
払込方法:一時、年、半年、月等
猶予期間:月払いの場合、翌月末日まで。年払い、半年払いの場合、翌々月の契約応答日まで
復活:未払いにより失効した契約を保険料を払うことで元に戻す(失効前の保険料)ことが可能。健康状態によっては復活不可
▫️配当金
死差益、利差益、費差益による剰余金が財源。
有配当保険:3利源配当
準有配当保険:利差益のみ
無配当保険:配当なし
▫️契約
契約者または被保険者は告知義務がある。
告知受領権:保険会社と診査医
告知義務違反:解除権は締結から5年まで。解除原因があることを把握してから1ヶ月以内
責任開始日:申込、告知、初回保険料払込の全てが揃った日
▫️必要補償額
必要補償額=余命までの支出総額ー総収入
支出:末子独立までの遺族生活費+配偶者生活費+葬儀費等
収入:社会保障(遺族年金等)+金融資産
▫️定期保険
一定期間内の死亡または高度障害状態で支払い。保険料は掛捨て。
平準定期保険:満期まで保険金額が一定
逓減定期保険:満期に近づくにつれて保険金額が減少
逓増定期保険:満期に近づくにつれて保険金額が増加
収入保障保険:年金形式で支払い。一時金も可
▫️終身保険
保障が一生続く。解約返戻金が高め。
・定期保険特約付終身保険
全期型:終身保険の支払期間と定期保険の支払期間が同じ
更新型:定期保険の支払期間が短い。更新可能だが更新毎に高くなる。告知不要。健康状態にかからない
▫️養老保険
一定期間内に死亡した場合は死亡保険金、満期時に生存していたら満期保険金を受け取れる。
▫️変額保険
保険会社の運用成績によって支払金額が変わる。
死亡保険金と高度障害保険金には基本保証金(最低保証)があるが、解約返戻金と満期保険金には最低保証はない。
▫️特約
・特定疾病保障保険特約
がん、急性心筋梗塞、脳卒中の診断となり所定の状態になった場合に前倒しで死亡保険金が支払われる。
・リビングニーズ特約
被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合に前倒しで死亡保険金が支払われる。特約保険料は必要なし。
・先進医療特約
療養時に厚生労働大臣の定める施設かつ先進医療を受けた時に給付金が支払われる。
▫️契約継続
払済保険:払込を中止した時点の解約返戻金を元に一時払いで契約変更。保険期間は元の契約と同等で保険金が少なくなる。特約は消滅
延長保険:保険金を変えずに保険期間が短くなる。特約は消滅
▫️生命保険料控除
以下の3区分それぞれ所得税40,000円、住民税28,000円まで。
・一般生命保険料控除
・個人年金保険料控除
・介護医療保険料控除
※災害割増特約、障害特約、少額短期保険は対象外。住民税の合計は70,000円まで
※2012年以降の契約が上記の条件となる
▫️税金
契約者が亡くなった場合:相続税
契約者が受け取る場合:所得税、住民税
契約者が生存かつ別の人が受け取る場合:贈与税
非課税となる保険金や給付金:
入院給付金、高度障害保険金、介護保険金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金等
損害保険
損害保険の分類。
損害保険
- 火災保険
- 地震保険
- 自動車保険
- 傷害保険
- 賠償責任保険
超過保険:保険金額>保険価額(実損填補)
全部保険:保険金額=保険価額(実損填補)
一部保険:保険金額<保険価額(比例填補)
▫️火災保険
対象:火災、落雷、風災、消防活動による水漏れ等
対象外:地震、噴火、津波
支払額:保険金額が80%以上は実損填補、80%未満は比例填補
失火責任法:刑過失による火災では隣家に賠償責任は負わなくて良い
※借家を消失させた場合は、家主に対して損害責任がある
▫️地震保険
火災保険の対象外部分を補填。火災保険とセットで契約する。
対象物:住宅と家財。1組30万円を超える貴金属は対象外
保険料:所在地、建物の構造による(どの保険会社でも同一)。免震建築物割引等がある。割引の重複は不可
保険金:火災保険の30~50%で設定。(上限:住宅5,000万円、家財1,000万円)
支払:損害の程度(全損、大半損、小半損、一部損)による
・地震保険料控除
所得税:最高50,000円(保険料全額)
住民税:最高25,000円(保険料の1/2)
▫️自動車保険
・自賠責保険(加入必須)
対象:対人賠償事故。被害者の補償のみ
限度額:死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害4,000万円
・任意保険
対人賠償保険:自賠責を超える部分
対物賠償保険:他人の物に対して
搭乗者傷害保険:運転手、同乗者が死傷した際
自損事故保険:運転者の単独事故
無保険車傷害保険:加害者が無保険や賠償ができない場合
車両保険:事故、盗難、火災、台風、いたずら等による損害
人身傷害補償保険:被保険者が死傷した場合に過失にかかわらず損害額を補償
▫️傷害保険
普通傷害保険:国内外の日常生活で起こる傷害を補償
交通事故傷害保険:国内外の交通事故(電車等も含む)による傷害を補償
国内旅行傷害保険:旅行中の細菌性食中毒も含まれる
海外旅行傷害保険:旅行中の地震、噴火、津波による傷害も含まれる
▫️賠償責任保険
個人賠償責任保険:日常生活での事故による対人、対物への補償。家族も対象
PL保険:企業が製造、販売した製品の欠陥により、他人に障害を与えた場合
施設所有者賠償責任保険:施設の不備や業務遂行中に生じた事故
受託者賠償責任保険:預かった物を壊したり失くした場合
▫️税金
損失補填を目的としているため、損害保険金は非課税。
第三の保険
第三の保険の分類。
第三分野の保険
- 医療保険
- がん保険
- 介護保障保険
- 所得補償保険
▫️医療保険
病気や怪我による入院、手術に備える保険。1回の入院について支払日数に限度がある(退院日の翌日から180日以内の同じ病気での再入院は前回と合わせ1回とみなす)。
▫️がん保険
がんに限定した保険。
給付内容:診断給付金、手術給付金、入院給付金(支払日数制限なし)
免責期間:加入後90日間程度が設けられる
▫️介護保障保険
寝たきりや認知症が一定期間続いた場合の保険。社保の介護保険と連動したものと民間独自のものがある。
▫️所得補償保険
病気や怪我で仕事ができなくなった場合の保険。
あとがき
FP所有者の割合は保険業界がトップのようなので、本業で必要な方はこの分野がメインなのかもしれません。
保険内容を吟味して契約している方にも身近な内容なのかもですが、私は民間の保険にはほぼ加入していないので、なんとなく聞いたことはあるかな程度の内容が多かったです。自身が加入する時が来たら改めて見直したいですね。
生保の保険金にはしっかり課税されますが、入院/障害/介護関連は非課税になったり、損保は基本非課税だったり、一定の配慮はされているんだなと思いました。