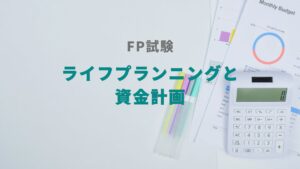FP勉強ノート。
E 不動産
試験範囲
- 不動産の見方
- 不動産の取引
- 不動産に関する法令上の規制
- 不動産の取得・保有に係る税金
- 不動産の譲渡に係る税金
- 不動産の賃貸
- 不動産の有効活用
- 不動産の証券化
- 不動産の最新の動向
土地価格
実勢価格:時価。売主と買主の合意で決まる
公示価格:取引価格の指標
標準価格:公示価格の補足
相続税路線価:相続税、贈与税の基準価格
固定資産税評価額:固定資産税、不動産取得税の基準価格
| 決定機関 | 基準日 | 公表日 | 評価割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 公示価格 | 国土交通省 | 毎年1/1 | 3月下旬 | 基準 |
| 標準価格 | 都道府県 | 毎年7/1 | 9月下旬 | 基準 |
| 相続税路線価 | 国税庁 | 毎年1/1 | 7/1 | 80% |
| 固定資産税評価額 | 市区町村 | 3年毎1/1 | 3月か4月 | 70% |
▫️鑑定評価方法
取引事例比較法:似た取引事例を参考に補正
原価法:再調達原価を求め、減価修正を加える
収益還元法:将来生み出すであろう純利益と売却価格から算出
直接還元法:単年度の純利益を一定率で割り戻す
DCF法:複数年の純利益を現在価値に割り戻す
不動産登記
▫️不動産登記簿の構成
表題部:所在地、面積、構造等
権利部
- 甲区:所有権について。保存、移転、差押等
- 乙区:抵当権、先取特権、賃借権等
▫️不動産登記の効力
対抗力:自身が当該不動産の所有者であると主張できる
公信力:ない。登記の内容を信じて取引して損害を受けても保護されない
不動産取引
▫️宅地建物取引業法
宅地建物取引業:宅地建物の売買、交換、賃貸の媒介及び代理
→ 都道府県知事または国土交通大臣からの免許が必要
※自ら行う賃貸(賃借業)は該当しない。自身アパートを貸すのは免許不要
宅地建物取引業者
宅地建物取引士:従業員5人に対し1人以上の設置が必要
重要事項説明:契約前に宅地建物取引士が書面で説明(承諾があれば電子提供も可)
・媒介契約
| 複数業者へ依頼 | 自己発見取引 | 契約有効期間 | 報告義務 | 登録義務 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | OK | OK | なし | なし | なし |
| 専任媒介契約 | NG | OK | 3ヶ月以内 | 1回以上/2週 | 7日以内 |
| 専属専任媒介契約 | NG | NG | 3ヶ月以内 | 1回以上/1週 | 5日以内 |
▫️売買契約
手付金:契約時に買主から売主に支払われる。解約手付
金額:宅建業者が売主の場合、売買代金の20%が上限
解約時
買主:手付金を放棄
売主:手付金の2倍を支払(手付金返却+同額支払)
※契約解除は相手方が契約履行着手前まで
危険負担:建物引渡し前に地震や火災等で建物が消失した場合、買主は代金支払いを拒むことができる(履行拒絶権)
売主担保責任:売主が契約内容に適合しない建物を引き渡した場合、買主は履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除が可能(不適合を知ってから1年以内に通知)
壁芯面積:壁の中心線の内側面積。建築基準法の床面積。一戸建て
内法面積:壁の内側の面積。マンション区分所有
法令
▫️借地借家法
借地権:建物を建てるために土地を借りる権利
| 契約期間 | 更新 | 利用目的 | 契約方法 | 契約終了後 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年以上 | 初回20年以上 以降10年以上 | 制限なし | 制限なし | 更地 |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | なし | 制限なし | 書面 | 更地 |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | なし | 事業用のみ | 公正証書のみ | 更地 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | なし | 制限なし | 制限なし | 建物付 |
借家権:建物を借りる権利
| 契約期間 | 更新 | 契約方法 | 契約終了 | |
|---|---|---|---|---|
| 普通借家権 | 1年以上 | 自動更新 | 制限なし | 賃借人:自由 賃貸人:正当な事由が必要 |
| 定期借家権 | 自由 | なし | 書面のみ | 賃貸人:1年から6ヶ月前に通知 (契約期間が1年以上の場合) |
▫️区分所有法
集会決議要件
一般的事項:区分所有者及び議決権の過半数
規約変更等:区分所有者及び議決権の3/4以上
建替:区分所有者及び議決権の4/5以上
▫️都市計画法
都市計画区域
- 線引区域
市街化区域:市街化済または10年以内に市街化予定
→ 13の用途地域がある(住居、商業、工業)
市街化調整区域:市街化を抑制
- 非線引区域:線引区域以外
・開発許可制度
開発行為(建築目的の土地の区画形質変更)には都道府県知事の許可が必要。
市街化区域:1,000㎡以上で許可必要
市街化調整区域:規模に関わらず許可必要
非線引区域:3,000㎡以上で許可必要
▫️建築基準法
・用途制限
診療所、保育所等:どこでもOK
住宅、図書館等:工業専用地域はNG
幼稚園〜高校:工場地域はNG
大学、病院:工業地域と低層住居専用地域はNG
※敷地が2つ以上の用途地域に跨る場合は面積の大きい地域の制限を適用
・接道義務
建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある。
・セットバック
幅員が4m未満の場合、道路の中心線から2mの位置を道路境界線とする。
※建替時に道路境界線まで後退。セットバック部分は建蔽率や容積率の敷地面積に含まれない
・建蔽率
建蔽率=建築面積÷敷地面積
指定建蔽率:用途地域毎に指定される
※複数の地域に跨る場合、敷地面積で加重平均
建蔽率の緩和:角地で10%緩和、防火地域内での緩和がある
・容積率
容積率=延べ床面積÷敷地面積
指定容積率:用途地域毎に指定される
※複数の地域に跨る場合、敷地面積で加重平均
容積率の制限:前面道路の幅員が12m未満の場合、幅員と法定乗数による制限あり
高さ制限:低層住居専用地域等は10mまたは12mまで。日影制限は住宅地域のみ
・防火規制
建物密集地域等の火災延焼防止。
防火地域:耐火建築物で建築必要
準防火地域:耐火建築物または準耐火建築物で建築必要
※複数の地域に跨る場合、規制の厳しい方を適用
・農地法
農地を農地以外に転用する場合、都道府県知事の許可が必要。
※市街化区域内の農地は農業委員会に届出をすればOK
税金
取得時:不動産所得税、登録免許税、消費税、印紙税
保有時:固定資産税、都市計画税
売却時:所得税(譲渡所得)、住民税
賃貸時:所得税(不動産所得)、住民税
| 対象 | 納税義務者 | 課税主体 | 課税標準 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産所得税 | 購入、贈与等 | 不動産取得者 | 都道府県 | 固定資産税評価額 | 3% |
| 登録免許税 | 不動産登記 | 売主と買主が連帯 | 国 | 同上 | 0.4%、2% |
| 固定資産税 | 保有不動産 | 1/1時点の所有者 | 市町村 | 同上 | 1.4% |
| 都市計画税 | 市街化区域内 | 1/1時点の所有者 | 市町村 | 同上 | 0.3%以内 |
不動産所得税
- 相続は対象とならない
- 宅地の場合、課税標準× 1/2
- 一定の新築住宅の場合、課税標準ー1,200万円
登録免許税
- 相続時も課税される(0.4%)
- 住宅は軽減税率あり
固定資産税
- 一般的に納税負担は売主と買主で所有期間に応じて按分
- 200㎡以内の住宅用地の場合、課税標準× 1/6(200㎡超の部分は1/3)
- 要件を満たした新築の場合、3~5年間120㎡まで税額が1/2
都市計画税
- 200㎡以内の住宅用地の場合、課税標準× 1/3(200㎡超の部分は2/3)
消費税
- 対象は建物の譲渡、居住用を除く貸付、仲介手数料
- 土地の譲渡、貸付、居住用賃貸物件の貸付は非課税
印紙税
- 売主と買主双方の契約書に印紙の貼付、消印が必要
- 印紙がなくても契約自体は有効
▫️所得税
譲渡所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)
特例
1.居住用財産の3,000万円特別控除
- 所有期間は問わない
- 親族への譲渡は対象外
- 居住終了から3年経過する日の12/31までに譲渡
- 前年、前々年に当該特例を受けていないこと
- 2.と併用可。3.は併用不可
2.居住用財産の軽減税率
- 1/1時点で10年超所有している居住用財産の譲渡が対象
- 6,000万円以下の部分に軽減税率適用(所得税10.21%、住民税4%)
- 1.と併用可。3.は併用不可
3.特定居住用財産の買換え
- 所有期間と居住期間が10年超かつ譲渡価格が1億円以下の場合が対象
- 床面積50㎡以上の居住用財産に買い替えた際の税金を翌年以降に繰り越せる
- 1.2.と併用不可
4.空き家の譲渡
- 相続で取得した家屋に居住者がいないかつ譲渡価格が1億円以下の場合が対象
- 特別控除3,000万円。相続人が3人以上の場合は、2,000万円
- 相続開始から3年経過する日の12/31までに譲渡
- 区分所有は対象外
不動産有効活用
▫️土地の有効活用方法
自己建設方式:所有者が資金調達、建設等全て実施
事業受託方式:所有者が資金調達し、事業はデベロッパーに任せる
等価交換方式:所有者が土地を提供、デベロッパーが建物建設。資金提供割合により権利を分ける
建設協力金方式:テナントから協力金を借り入れて建設費に充てる
定期借地権方式:一定期間土地を貸し出す
▫️不動産投資利回り
表面利回り:年間収入合計÷投資総額
→ 経費が考慮されていない(単純利回り)
純利回り:(年間収入合計ー年間諸経費)÷投資総額
→ 経費も考慮(実質利回り、NOI利回り)
あとがき
不動産は興味あったので概要を把握できて良かったです。
不動産関連は額が大きいこともあり、いざ自身が経験する際にはルールを理解し、しっかり控除も適用していきたいです。不動産の売買、賃貸、相続と生きていく上でどれかは経験することがほとんどでしょうから、このパートも覚えておくに越したことはない内容ですね。