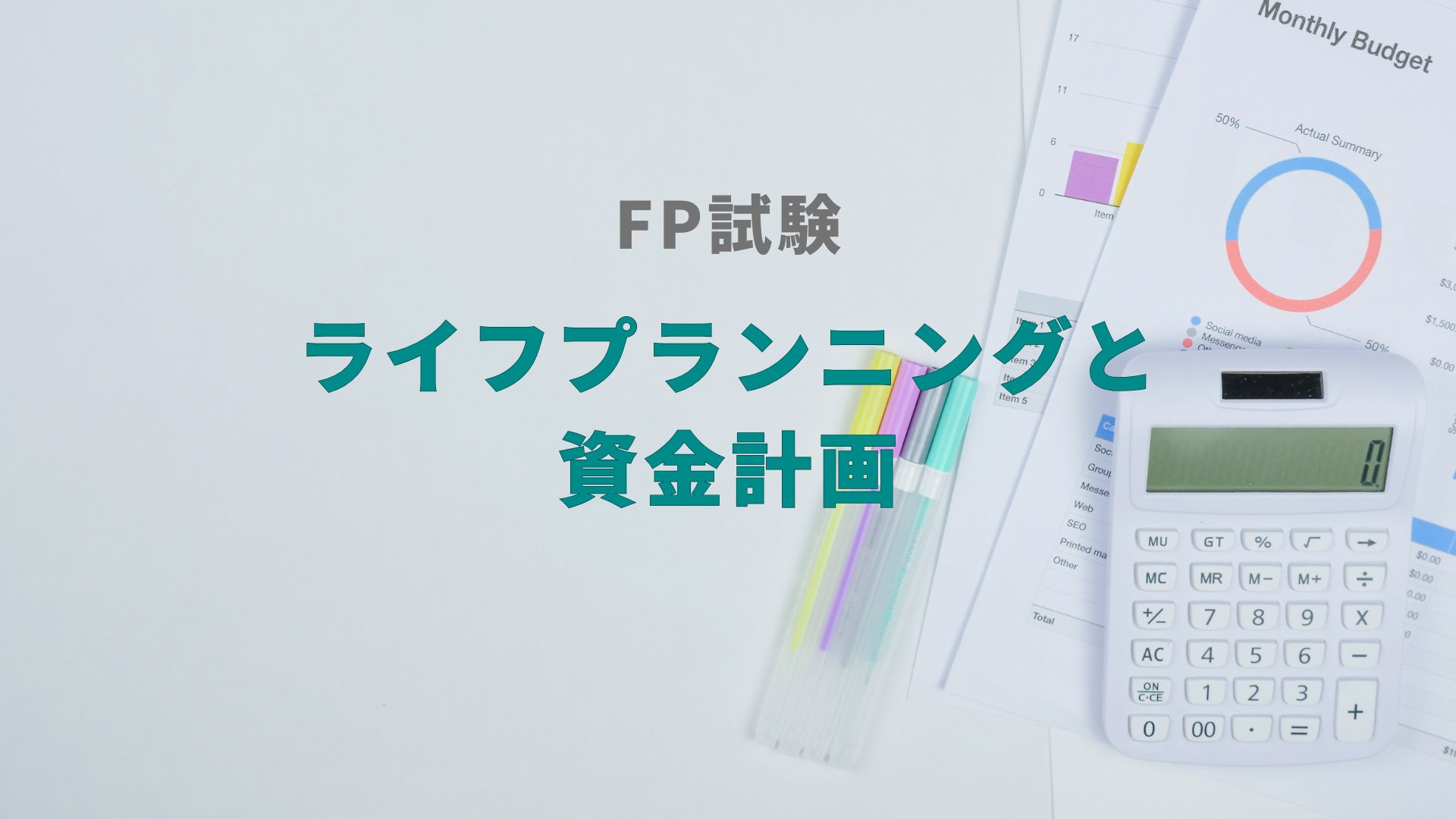FP勉強ノート。
社会保険等、リタイア時に関係するところはいずれ別途詳細に纏めたいなと考えています。
A ライフプランニングと資金計画
試験範囲
- ファイナンシャル・プランニングと倫理
- ファイナンシャル・プランニングと関連法規
- ライフプランニングの考え方・手法
- 社会保険
- 公的年金
- 企業年金・個人年金等
- 年金と税金
- ライフプラン策定上の資金計画
- ローンとカード
- ライフプランニングと資金計画の最新の動向
関連法規
▫️弁護士法
弁護士資格を持たないFPは、法律判断や法律事務を行えない
▫️税理士法
税理士資格を持たないFPは、税務相談や税務書類の作成を行えない
▫️金融商品取引法
金融商品取引業の内閣総理大臣の登録がないFPは、投資判断の助言を行えない
▫️保険業法
保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行えない
FPだけだと一般的な説明くらいしかできない。独占業務を持つ士業が優位。
ライフプランニング
▫️3大必要資金
- 教育資金
– こども保険(貯蓄、保障機能)
– 教育一般貸付
→ 最高350万円 。固定金利。最長18年
– 奨学金
→ 無利息:第一種。利息付:第二種 - 住宅取得資金
– 財形住宅貯蓄
– 財形住宅融資
→ 5年、固定金利。財形貯蓄の10倍以内。最高4,000万円。価格の90%以内
– フラット35
→ 融資実行日の金利。最高8,000万円。価格の100%。申込時70歳未満、完済時80歳以下
→ 繰上げ返済(窓口:100万円以上、ネット:10万円以上、手数料無料)
→ 保証人、保証料不要
– 金利
→ 固定金利、変動金利
→ 固定金利選択型(固定→変動or固定)
– 返済方法
→ 元利均等返済、元金均等返済
→ 繰上げ返済(返済期間短縮型、返済額軽減型)
→ 借換え(×民間→公的)
→ 団体信用生命保険 - 老後資金
– 退職金、年金、貯蓄
▫️プランニングツール
- ライフイベント表
- キャッシュフロー表
- 個人バランスシート
▫️6つの係数
- 終価係数
- 原価係数
- 年金終価係数(積立)
- 減債基金係数(積立)
- 資本回収係数(取り崩し)
- 年金原価係数(取り崩し)
社会保険
社会保険は以下のように分類される。
社会保険
– 医療保険
→ 健康保険
→ 国民健康保険
→ 後期高齢者医療制度
– 介護保険
– 年金保険
→ 国民年金
→ 厚生年金
労働保険
– 労働者災害補償保険
– 雇用保険
▫️健康保険
会社員とその家族が対象。
保険者:全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合(組合健保)
保険料:労使折半
療養給付:小学生まで2割、70歳まで3割、75未満2割(所得によって3割)負担
高額療養費:標準報酬月額によって自己負担額超過分について請求後返金
出産育児一時金:50万円/児
出産手当金:出産前42日、出産後56日。12ヶ月間給与平均の2/3を休んだ日分
傷病手当金:3日以上連続で休んだ後、4日目から通算1年6ヶ月間支給。給与平均2/3
埋葬料:5万円
・任意継続
退職後2年間は退職前の健康保険に加入が可能。2ヶ月以上加入していること、退職日翌日から20日以内に申請することが要件。保険料は全額負担となる。
退職者は、任意継続 or 国民健康保険加入 or 被扶養者となるを選択。
▫️国民健康保険
自営業者や未就業者等が対象。
保険者:都道府県と市区町村の共同、国民健康保険組合
保険料:市区町村による。前年の所得等により計算
給付内容:健康保険とほぼ同様。出産手当金、傷病手当金は出ない
▫️後期高齢者医療制度
75歳以上。保険料は年金から天引き。医療費1割負担(所得次第で2割、3割)。
▫️介護保険
第1号被保険者:65歳以上。年金から天引き
第2号被保険者:40~65歳未満。健康保険、国民健康保険に準ずる
自己負担:原則1割(所得次第で2割、3割)
▫️労働者災害保障保険(労災保険)
業務上における病気、怪我、死亡等に対しての給付。通勤途上も含まれる。
対象者:全ての労働者(経営者は含まない)
保険料:全額事業主負担
休業補償給付:4日目から給付基礎日額の60%
傷病補償年金:療養開始後1年6ヶ月経過しも治らない場合(傷病等級1~3級)
経営者や自営業者は特別加入制度により任意加入が可能。
▫️雇用保険
失業時の給付や再就職の援助。
対象者:全ての労働者(経営者は含まない)
保険料:事業主と労働者で負担
基本手当:失業保険。離職前6ヶ月間の賃金の45~80%
自己都合、定年退職の場合、最短90日、最長150日
会社都合、倒産の場合、最短90日、最長330日
受給要件:離職前の2年の内、通算12ヶ月以上被保険者であること(会社都合の場合はそれぞれ半分)
ハローワークに離職票を提出、休職申込を実施後、7日間の待期期間がある。自己都合の場合、さらに2ヶ月の給付制限あり(→2025年4月から給付制限が緩和された)
就職促進給付:基本手当受給完了前の再就職時に再就職手当。アルバイトの場合は就業手当
雇用継続給付:
高年齢雇用継続給付:5年以上の被保険者かつ60~65歳未満。75%未満の給料となった場合、賃金の最大15%支給
介護休業給付:93日3回まで休業前賃金の67%支給
育児休業給付:
育児休業給付金:1歳未満。休業前賃金の67%、6ヶ月後は50%支給
出生時育児休業給付金:産後8週までの4週以内。休業前賃金の67%
教育訓練給付:指定の講座を受けた場合に費用の一部を支給
年金制度
年金は以下のように分類される。
国民年金
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
厚生年金保険
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
その他年金
- 企業年金
- iDeCo
- 付加年金
- 国民年金基金
- 小規模企業共済
第1号被保険者:第2号、第3号以外の人
第2号被保険者:会社員、公務員(厚生年金)
第3号被保険者:第2号に扶養されている配偶者
20歳から60歳未満は強制加入。第2号は会社員なら20歳未満も対象。
▫️国民年金
保険料:16,980円/月
納付期限:翌月末日。当月末の口座振替、前納(半年、1年、2年)は割引あり
追納:2年以内。保険料の免除、猶予を受けた場合は10年以内
免除/猶予:所得等により全額〜1/4の免除、納付の猶予が可能
支給日:偶数月の15日。前月までの2ヶ月分。受給権発生の翌月から
・老齢基礎年金
要件:受給資格期間10年以上。65歳から。資格期間には免除期間も含まれる
金額:816,000円/年。未納、免除期間分は引かれる
繰上げ受給:60歳から。繰上げ月数×0.4%減額
繰下げ受給:75歳まで。繰下げ月数×0.7%増額
・障害基礎年金
受給要件:初診日に被保険者であること。障害認定日に障害等級1級、2級に該当すること
納付要件:全被保険者期間の2/3以上
金額:1級は、816,000円×1.25倍+子の加算額。2級は1.25倍がない
・遺族基礎年金
受給対象:子または子のある配偶者
納付要件:障害基礎年金と同様
金額:816,000円+子の加算額
寡婦年金:受給資格期間を満たした夫が亡くなった場合、10年以上の婚姻期間があった妻に支給
死亡一時金:3年以上の納付期間があり遺族が遺族既存年金を受け取れない場合。寡婦年金と併給不可
▫️厚生年金
保険料:標準報酬月額と標準賞与額の18.3%。労使折半
支給日:国民年金と同様
・老齢厚生年金
要件:老齢基礎年金の要件&厚生年金加入期間1年以上
金額:加入期間と収入による
繰上げ受給:老齢基礎年金と同時
繰下げ受給:老齢基礎年金と別にできる
加給年金:20年以上加入&配偶者または子がいる場合に加算
在職老齢年金:60歳以降の会社員。給与+年金が50万円/月を超えると減額
・障害厚生年金
受給要件:障害基礎年金に3級が加わる
納付要件:障害基礎年金と同様
金額:1級は、厚生年金報酬比例×1.25倍+配偶者加給年金額。2級は1.25倍がない。3級は配偶者加給もなし
一時金:厚生年金報酬比例額×2
・遺族厚生年金
受給対象:妻・夫・子>父母>孫>祖父母
金額:老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4。被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなす
中高齢寡婦加算:40歳以上65歳未満の子のない妻、遺族基礎年金を受け取れない妻に加算
▫️企業年金
確定給付型:厚生年金基金、確定旧企業年金
確定拠出型:企業型確定拠出年金
・企業型確定拠出年金
対象者:導入企業の従業員&70歳未満の厚生年金被保険者
拠出限度額:確定給付型年金実施なしだと55,000円/月。実施ありだと半額
▫️個人型確定拠出年金(iDeCo)
加入対象者:65歳未満
拠出限度額:自営業者等は68,000円/月。厚生年金被保険者、専業主婦は12,000~23,000円/月
控除:全額所得控除の対象
税金:運用益は非課税
▫️付加年金
第1号が対象。400円/月を上乗せして支払うことで納付月数×200円が老齢基礎年金に加算される。2年間年金を受給すれば元が取れる。
▫️国民年金基金
第1号が対象。掛金は確定拠出年金と合算して68,000円/月まで。付加年金と併用不可。
▫️小規模企業共済
従業員20人以下の個人事業主や経営者が対象。掛金は1,000~70,000円/月。
あとがき
社保と年金が複雑。
会社員だと健康保険と厚生年金に加入していて、会社側が処理しているので普段意識しない方が多いのではと思います。退職して離職期間がある場合は、健康保険をどうするか、雇用保険の受給をどうするか、国民年金を免除するのか、確定拠出年金の移管、といったことを考慮する必要があります。知らないと損することもあるので、この辺り中心に別途纏められたらと思います。
年金の受給も60歳まで繰上げして資産運用した場合、どの程度の利回りなら65歳(または繰下げの75歳)から受け取る場合より資金効率が良くなるのかといった検証もそのうちしてみたいなと考えています。年利数%で良いなら確実に繰上げ受給しますし、10%以上必要となると要検討ですね。年金制度も自身の寿命もどうなるか分かりませんし、減額されてもなるべく早めに手元に入るようにしたい気もします。