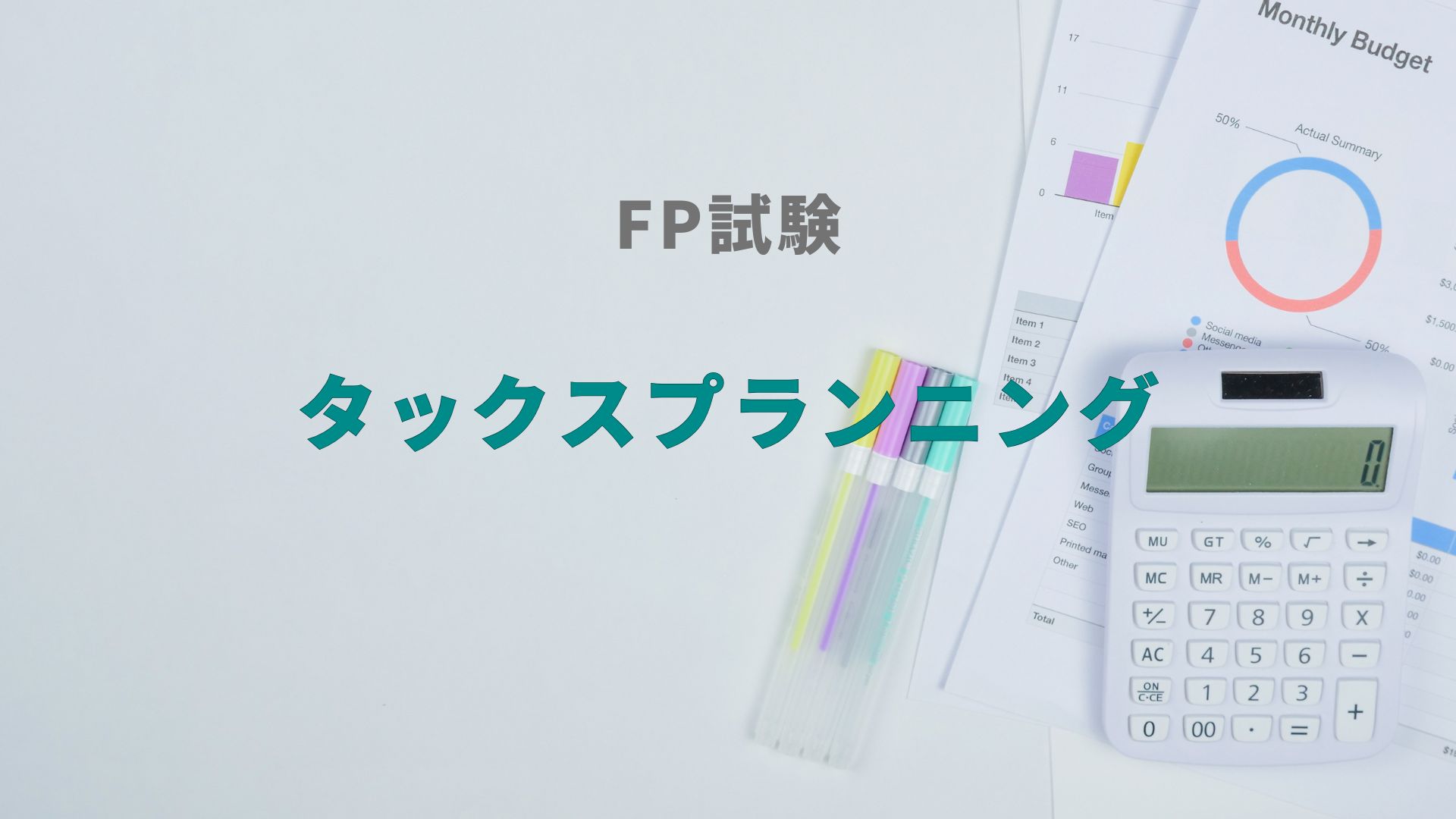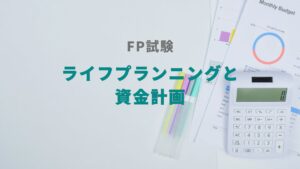FP勉強ノート。
D タックスプランニング
試験範囲
- わが国の税制
- 所得税の仕組み
- 各種所得の内容
- 損益通算
- 所得控除
- 税額控除
- 所得税の申告と納付
- 個人住民税
- 個人事業税
- タックスプランニングの最新の動向
分類
国税
直接税:所得税、法人税、相続税、贈与税等
間接税:消費税、酒税、印紙税等
地方税
直接税:住民税、事業税、固定資産税、不動産所得税等
間接時:地方消費税
・申告納税方式:自身で計算して収める
→ 所得税、法人税、相続税、贈与税等
・賦課課税方式:国や地方が計算して通知
→ 住民税、固定資産税等
・総合課税:総所得金額から計算
→ 給与所得、事業所得、不動産所得等
・分離課税:他の所得とは合算しない
- 申告分離課税:確定申告する
→ 退職所得、譲渡所得(土地、建物、株式等)
- 源泉分離課税:確定申告しない(源泉徴収)
→ 利子所得
所得税
個人が1/1~12/31に得た収入から経費を差し引いた所得に対してかかる税金。
▫️非課税対象
社会保険の給付金:雇用保険、障害年金、遺族年金等
通勤手当:15万円/月まで
生命保険の保険金:身体の傷害に起因するもの
損害保険の保険金:身体の傷害、資産の損害に起因するもの
▫️計算の流れ
1.利子所得、2.配当所得、3.事業所得、4.不動産所得、5.給与所得
6.退職所得、7.山林所得、8.譲渡所得、9.一時所得、10.雑所得
損益通算対象:3.不動産、4.事業、7.山林、8.譲渡
配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除等
195万円以下は5%、4,000万円超は45%
住宅ローン控除等
○STEP1
▫️利子所得
利子所得=収入金額
・預貯金、公社債
種別:源泉分離課税
税率:20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
・特定公社債(国債、公募社債、外貨建てMMF等)
種別:申告分離課税
→ 源泉徴収にすれば申告不要
▫️配当所得
配当所得=収入金額ー株式等を取得するための負債利子
・上場株式等
種別:総合課税
→ 申告分離課税の選択も可。源泉徴収にすれば申告不要
税率:20.315%(分離課税)
▫️事業所得
事業所得=総収入金額ー必要経費
総収入金額:その年に確定した収入金額(売掛金含む)
必要経費:原価、販売費、減価償却費、給与等
減価償却
定額法:毎年同額を計上
→ 個人は原則定額法。建物や建物付属設備、ソフトウェアも
定率法:1年目が最も多く年々減少
→ 法人は原則定率法
※使用期間が1年未満、価格10万円未満は減価償却対象外
種別:総合課税
▫️不動産所得
不動産所得=総収入金額ー必要経費
※賃貸収入が対象、売買は譲渡所得
総収入金額:賃料、礼金、更新料等(敷金等の返還予定のものは含まない)
必要経費:固定資産税、修繕費、管理費、減価償却費、借入金の利子等
種別:総合課税
▫️給与所得
給与所得=収入金額ー給与所得控除額
給与所得控除:162.5万円以下は55万円、850万円超は195万円
所得金額調整控除:(1,000万円上限の収入金額ー850万円)×10%
※給与収入が850万円超かつ、23歳未満の扶養親族ありか本人または扶養親族が特定障害者
種別:総合課税
→ 会社員は勤務先にて源泉徴収されるため申告不要(年収2,000万円超、複数の勤務先がある場合は申告必要)
▫️退職所得
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)× 1/2
※一時金が対象、年金形式の場合は雑所得
退職所得控除
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※最低80万円、1年未満は1年に切り上げて計算
種別:源泉分離課税(退職所得の受給に関する申告書を提出した場合)
→ 申告書未提出の場合は収入の20.42%課税。確定申告必要
▫️山林所得
山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除(50万円)
種別:申告分離課税
▫️譲渡所得
・土地、建物
1/1時点の所有期間が5年以下:分離短期譲渡所得
=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
種別:分離課税
税率:39.63%(うち住民税9%)
1/1時点の所有期間が5年超:分離長期譲渡所得
=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
種別:分離課税
税率:20.315%
※取得費が不明の場合は収入金額の5%を概算取得費とできる
・株式等
所有期間によらず株式等に係る譲渡所得
=総収入金額ー(取得費+譲渡費用+負債の利子)
種別:分離課税
税率:20.315%
・土地、建物、株式以外
所有期間が5年以下:総合短期譲渡所得
=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
種別:総合課税
所有期間が5年超:総合長期譲渡所得
=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額)
→ 1/2した額を総所得金額に合算
種別:総合課税
※特別控除額は短期と長期合わせて最高50万円
▫️一時所得
上記所得以外の一時的な所得。
対象:懸賞、競馬等の払戻金、契約者が受け取る生命保険の満期保険金、ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益
※宝くじは非課税
一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最高50万円)
→ 1/2した額を総所得金額に合算
種別:総合課税
▫️雑所得
上記以外の所得。
対象:公的年金の老齢給付、個人年金保険の年金、為替差益、講演料等
雑所得=公的年金等の雑所得+公的年金以外の雑所得
公的年金等:収入金額ー公的年金等控除額
公的年金以外:総収入金額ー必要経費
種別:総合課税
STEP2
▫️損益通算
損失(マイナスの所得)を利益と相殺できる。
対象:不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得
対象外:土地を取得するための借入金の利子(建物は対象)、株式による譲渡損失
※株式は分離課税として損益通算可能
・損失の繰越控除
損益通算でマイナスとなった場合、青色申告者は翌年以降3年間損失を繰り越せる。
・課税標準
損益通算後の合計所得金額から繰越控除をした総所得金額。
STEP3
▫️所得控除
・基礎控除
2,400万円以下:48万円
2,500万円超:適用なし
・配偶者控除
適用要件
納税者:合計所得金額が1,000万円以下
配偶者:納税者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下
控除額
所得900万円以下:38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)
配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(最大38万円)
・扶養控除
合計所得金額が48万円以下の16歳以上の扶養親族がいる場合。
控除額
一般扶養親族:38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
老人扶養親族(70歳以上):同居58万円、別居48万円
・社会保険料控除
納税者及び生計を一にする親族にかかる社会保険料を控除可能。
対象:国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金、国民年金基金の掛金等
控除額:全額
・小規模企業共済等掛金控除
対象:小規模企業共済、確定拠出年金の掛金等
控除額:全額
・生命保険料控除
一般生命保険料控除:死亡保険、学資保険等
介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、介護保険等
個人年金保険料控除:税制適格特約が付与された個人年金保険
控除額:計算式による一定金額(各控除最高4万円まで)
・地震保険料控除
対象:居住用家屋、生活用動産
控除額:全額(最高5万円)
・医療費控除
納税者及び生計を一にする親族にかかる医療費を控除可能。
対象:医師または歯科医師による診察費及び治療費、薬代、出産費用、通院のための交通費
対象外:美容整形費用、サプリ系、健康診断費用
※年内に支払った金額。健康診断で重大な疾病が見つかり治療した場合は健康診断費用も対象
控除額:医療費総額ー保険金ー10万円(または総所得金額の5%の低い方)
※上限200万円。確定申告時に明細書の添付が必要(年末調整対象外)
セルフメディケーション税制
対象:健康維持促進、疾病予防にかかるスイッチOTC医薬品等の購入費
控除額:支出額ー12,000円(最高88,000円)
STEP4
▫️所得税額
総所得金額から所得控除額を引いた課税総所得金額に超過累進税率を適用する。
税額(総合課税)
所得195万円以下:課税総所得金額×5%
4,000万円超:課税総所得金額×45%ー4,796,000円
※最低と最大のみ。他は速算表で確認
STEP5
▫️税額控除
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンの年末残高に応じて一定額を控除可能。
要件
- 50㎡以上かつ1/2以上が住居用(取得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上)
- 合計所得金額が2,000万円以下(40~50㎡の場合は1,000万円以下)
- 返済期間が10年以上(繰上げ返済で10年未満となると対象外)
- 住宅取得日から6ヶ月以内に居住開始し、年末まで居住している
- 住宅ローン適用の初年度に確定申告が必要(翌年からは年末調整可能)
控除額:ローン残高の0.7%
新築:認定住宅は残高上限4,500万円
中古:残高上限3,000万円(認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)
控除期間:新築13年、中古10年
・配当控除
対象:総合課税とした配当所得
対象外:分離課税として配当所得、J-REITの分配金、NISA口座の配当等
控除額:配当所得の10%(課税総所得金額が1,000万円超の場合、超過部分は5%)
▫️確定申告
前年の所得税額を計算し、2/16~3/15に申告、納付。
・青色申告制度
複式簿記に基づいて帳簿を作成、申告することで節税等が可能。
対象:不動産所得、事業所得、山林所得
要件:3/15までに青色申告承認申請書を納税地の税務署長に提出
※1/16以降に開業した人は業務開始から2ヶ月以内
特典
青色申告特別控除:所得金額から最高55万円(e-Taxの場合65万円)
→ 事業所得または事業規模の不動産所得が対象
青色事業専従者給与の経費化:家族の給与を経費にできる
純損失の繰越控除:翌年以降3年間
個人住民税
前年の所得に対してその年の1/1に住民票がある都道府県または市区町村で課税。
均等割:所得にかかわらず一定額が課税
所得割:所得に比例して課税(税率10%)
普通徴収:年4回の分納(事業所得者向け)
特別徴収:毎月給与から徴収(給与所得者向け)
個人事業税
一定の事業所得または不動産所得のある個人が都道府県に納税。
課税対象額:事業所得+不動産所得ー290万円(事業主控除)
税率:3~5%(業種による)
※所得が控除額を超える場合は、3/15までに申告(所得税の確定申告をしていれば申告不要)
あとがき
簡単にしか纏めてないのに結構複雑。
一般会社員だと源泉徴収され流れに沿って年末調整すれば完了なのであまり意識しておらず、なんとなく知っている程度の内容も多かったです。退職して離職期間ができたり、個人事業主になったりすると意識せざるを得ない部分も増えてきそうです。
配当所得を分離課税とした方が得か総合課税とした方が得かとかはリタイア後に気になる部分ですので、そのうち整理できたら良いなと思います。総所得金額がそこまで大きくなければ総合課税の方が良いのでしょうけど、分離課税で源泉徴収してもらった方が楽ではありますよね。