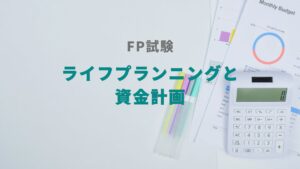FP勉強ノート。
株式、債券、金融商品の税金等、投資家向けのメインパート。
C 金融資産運用
試験範囲
- マーケット環境の理解
- 預貯金・金融類似商品等
- 投資信託
- 債券投資
- 株式投資
- 外貨建商品
- 保険商品
- 金融派生商品
- ポートフォリオ運用
- 金融商品と税金
- セーフティネット
- 関連法規
- 金融資産運用の最新の動向
基本知識
▫️経済・景気指標
・GDP(国内総生産)
国内の経済活動で生み出された財・サービスの付加価値の合計。
発表:内閣府が年4回
・景気動向指数
先行指数:新規求人数、新設住宅着工床面積、実質機械受注等
一致指数:鉱工業生産指数、有効求人倍率等
遅行指数:法人税収入、家計消費支出、完全失業率
発表:内閣府が毎月
CI:景気変動の大きさやテンポを測定
DI:景気の各経済部門への波及度を測定
・日銀短観(全国企業短期経済観測調査)
上場企業や中小企業への現状と3ヶ月後の景気動向に関するアンケートの集計結果。
業況判断DI:3ヶ月後の業況が良いと答えた割合 ー 悪いと答えた割合
発表:日本銀行が年4回
・マネーストック統計
個人、金融機関以外の法人、地方公共団体等が保有する通貨の総量。
発表:日本銀行が毎月
・物価指数
企業物価指数:企業間で取引される商品等の価格変動を表す
発表:日本銀行が毎月
消費者物価指数:一般消費者が購入する商品やサービスの価格変動を表す
発表:総務省が毎月
▫️景気
インフレ:物価が継続的に上昇(貨幣価値の下落)
デフレ:物価が継続的に下落(貨幣価値の上昇)
・景気と金利
一般的に、景気が良い→金利上昇、景気が悪い→金利下落。
・物価と金利
一般的に、インフレ→金利上昇、デフレ→金利下落。
・為替と金利
一般的に、円高→金利下落、円安→金利上昇。
・景気と株価
一般的に、景気が良い→株価上昇、景気が悪い→株価下落。
・内外金利差と為替
一般的に、日本の金利>諸外国の金利→円高、日本の金利<諸外国の金利→円安。
▫️金融市場
短期金融市場:取引期間が1年未満
- インターバンク市場:金融機関のみ(手形市場、コール市場等)
- オープン市場:一般企業も参加可能
長期金融市場:取引期間が1年以上
- 証券市場:株式市場、債券市場等
▫️新発10年国債利回り
長期金利の指標で、住宅ローン金利や企業の長期資金借入利率の基準となる。
▫️金融政策
物価安定等を目的に日本銀行が行う政策。
公開市場操作:短期金融市場で国債等の売買を行い金融市場の資金量を調整
売りオペレーション:日銀が債券等を売る→資金量減少→金利上昇→物価下落
買いオペレーション:日銀が債券等を買う→資金量増加→金利下落→景気上昇
預金準備率操作:預金準備率を操作して金融市場の資金量を調整
※金融機関は日本銀行に一定割合の預金を預ける義務がある
▫️財政政策
景気対策等を目的に国や地方公共団体が行う政策。公共投資、給付、減税等。
法制度
▫️預金保険制度
金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度。ペイオフ。
対象機関:国内に本店のある金融機関
※海外支店が対象外。外国銀行の日本支店も対象外
保護対象:預貯金、定期積立等
※外貨預金、譲渡性預金は対象外
保護範囲:
決済用預金(当座預金等):全額保護
決済用預金以外:1金融機関毎に元本1,000万円までとその利息
決済用預金の要件は、無利息・要求払い・決済サービスを提供できること。
▫️日本投資者保護基金
証券会社が加入していて、破綻等により投資家が損害を被った際に補償される。
補償対象:株式、公社債、投資信託、株式の信用取引保証金等
※銀行で購入した投資信託、FXの証拠金等は対象外
補償金額:最大1,000万円
証券会社には分別管理義務があり、証券会社が破綻しても投資家の金融資産に本来は影響はない。物別管理義務違反等で損害を被った場合のための補償。
▫️金融サービス提供法
金融商品販売業者は、顧客に元本割れリスク等の重要事項説明をする義務がある。説明義務を怠り、顧客が損害を被った場合は損害賠償責任が発生する。
▫️消費者契約法
事業者の不適切な行為により、消費者が誤認等して契約を申し込んだ場合は取消が可能。保護されるのは個人のみ。金融サービス提供法にも抵触する契約は双方の規定が適用される。
▫️金融商品取引法
投資家を保護するための法律。特定投資家(プロ)と一般投資家(アマチュア)に規制が分かれる。
金融証券取引業者が守るべきルール
・適合性の原則:顧客の属性、契約する目的に対して不適切な勧誘は行えない
・断定的判断の提供禁止:確実に儲かると誤認させるようなことはNG
・広告等の規制:一定の表示が必須で誇大広告はNG
・契約締結前の書面交付義務:手数料、リスク等について書面を交付しての説明が必須
・損失補填の禁止:顧客の損失を業者が補填するのはNG。約束するのもNG
※特定投資家は、適合性の原則や書面交付義務等が除外となる
▫️金融ADR制度
金融機関と顧客の間で生じたトラブルを指定紛争解決機関にて、裁判外の方法で解決を図る制度。
指定紛争解決機関:全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会等
利用手数料:原則無料
貯蓄型金融商品
預貯金。元本が保証されていていつでも引き出し可能。(預金:銀行、貯金:ゆうちょ銀行、農協)
利率:元本に対する利子の割合
利回り:元本に対する1年あたりの収益。(収益合計÷預入年数)÷元本
単利:元利合計=元本×(1+年利率×預入期間)
複利:元利合計=元本×(1+年利率)^ 年数
※利子も新たな元本とみなして次の利子を計算
固定金利:満期まで金利が一定
変動金利:市場金利の変化に応じて金利が変動
▫️銀行の主な金融商品
流動性預金
- 普通預金:変動金利。利払いは半年毎
- 貯蓄預金:預金残高が基準残高を上回っていると普通預金より高い金利が適用
定期性預金
- スーパー定期:固定金利
→ 預入期間が3年未満:単利型のみ
→ 預入期間が3年以上:半年複利型も選択可
- 大口定期預金:固定金利。単利型のみ。預入金額が1,000万円以上
- 期日指定定期預金:固定金利。1年複利。預け入れて1年後、満期日を指定できる
▫️ゆうちょ銀行の主な金融商品
流動性貯金
- 通常貯金:変動金利。利払いは半年毎
- 通常貯蓄貯金:貯金残高が基準残高を上回っていると通常貯金より高い金利が適用
定期性貯金
- 定額貯金:固定金利。半年複利。6ヶ月以降自由満期。最長10年。預入期間に応じた金利が預入時に遡って適用
- 定期貯金:固定金利
→ 預入期間が3年未満:単利型のみ
→ 預入期間が3年以上:半年複利型のみ
預入限度額:通常、定期それぞれ1,300万円までの計2,600万円
債券
額面価格:債券の券面に記載される金額。売買する際の最低単位
発行価格:債券を新規発行する際の価格
償還期限:債券の額面金額が最終償還される日(返済期限、満期日)
表面利率:債券の額面金額に対して毎年支払われる利息の割合(クーポンレート)
債券の分類。
国債:国が発行
地方債:地方公共団体が発行
社債:事業会社が発行
金融債:金融機関が発行
利付債:定期的に利子が支払われる
割引債:利子なし。発行価格<画面金額で発行
新発債:新規発行
既発債:発行済。市場で取引される
円建て債券:払込、利払、償還が円貨
外貨建て債券:払込、利払、償還が外貨
▫️発行価格
額面100円あたりの価格。
パー発行:100円(額面金額と同じ)
アンダー・パー発行:100円未満
オーバー・パー発行:100円超
▫️個人向け国債
毎月以下の3種類が発行される。
償還期限10年:変動金利型。基準金利×0.66。
償還期限5年:固定金利型。基準金利ー0.05%。
償還期限3年:固定金利型。基準金利ー0.03%。
※0.05%の金利が保証されていてそれ以下の場合は0.05%となる
中途解約:1年経過後から可能。直近2回分の利息相当額が引かれる
▫️利回り
投資額に対する利息と償還差損益の割合。
直接利回り:投資額に対する毎年の利息収入
表面利率÷購入価格
応募者利回り:新発債を償還まで保有
(表面利率+(額面価格ー発行価格)÷償還期限)÷発行価格
最終利回り:既発債を償還まで保有
(表面利率+(額面価格ー購入価格)÷残存年数)÷購入価格
所有期間利回り:償還前に売却
(表面利率+(売却価格ー購入価格)÷所有年数)÷購入価格
▫️リスク
価格変動リスク:
金利上昇 → 価格下落、利回り上昇
金利下落 → 価格上昇、利回り下落
信用リスク:デフォルト、債務不履行
低リスク → 高価格、低利回り
高リスク → 低価格、高利回り
投資適格債:格付けBBB以上
投資不適格債:BB以下。ジャンク債、ハイ・イールド債
※格付会社がAAA〜Dまで等で債券の格付けを行っている
株式
▫️株主の権利
議決権:経営参加権
剰余金分配請求権:利益の分配を受ける権利
残余財産分配請求権:会社解散時、持株に応じて財産の分配を受ける権利
▫️東京証券取引所
プライム市場:大企業向け。流動性やガバナンス等の条件を満たす企業
スタンダード市場:中規模企業向け。プライムよりは条件緩和
グロース市場:新興企業向け。高い成長が期待できる企業
▫️取引
指値注文:売買価格を指定する
成行注文:売買価格を指定しない(その時の価格で売買)
※指値より成行の取引が優先される
※指値でもより有利な価格で取引が成立することもある
約定日:売買が成立した日
決済日:約定日を含めて3営業日目。受渡日
▫️指標
・相場指標
日経平均株価:代表的な225銘柄の平均株価。株価換算指数で調整しているが値嵩株の影響が大きい
東証株価指数(TOPIX):東証上場銘柄の時価総額加重型。時価総額100億円未満を除く
・個別銘柄指標
PER(株価収益率):株価÷1株あたり純利益
低い→割安、高い→割高
PBR(株価純資産倍率):株価÷1株あたり純資産
低い→割安、高い→割高
※1倍未満は解散価値より株価が低い状態
ROE(自己資本利益率):当期純利益÷自己資本
高い方が資本効率が良い(少ない自己資本で稼げる)
配当利回り:1株あたり配当金÷株価
高い方が配当利回りが良い
配当性向:配当金総額÷当期純利益
高い方が株主還元率が良い(低い方が支払いが少ない)
自己資本比率:自己資本÷総資本
高い方が返済不要の資本の割合が多い(低いと負債が多い)
投資信託
多数の投資家から資金を集め、1つの基金として専門家が株式や不動産に投資し、得た利益を投資家に分配する仕組みの金融商品。
投資信託の分類。
公社債投資信託:株式なし
株式投資信託:株式あり
追加型(オープン型):いつでも購入可能
単位型(ユニット型):募集期間中のみの購入
オープンエンド型:いつでも解約可能
クローズドエンド型:解約不可(市場で他の投資家に売却、換金は可能)
パッシブ運用(インデックス運用):ベンチマーク連動型
アクティブ運用:ベンチマークを上回る運用成績を目指す
- トップダウン・アプローチ:マクロ的な投資環境から資産配分、銘柄選定
- ボトムアップ・アプローチ:個別銘柄分析で選定
→ グロース型:成長重視
→ バリュー型:割安銘柄
ETF(上場投資信託):上場株式同様に売買可能
J-REIT(上場不動産投資信託):投資先が不動産
▫️契約型投資信託
受益者:投資家
販売会社:証券会社、銀行等
→ 投資信託の募集、販売。受益者への分配金支払。目論見書、運用報告書の交付
委託者(運用会社):投資信託会社
→ 運用の指図。目論見書、運用報告書の作成
受託者(管理会社):信託銀行等
→ 株式、債券等への投資。信託財産の管理
トータルリターン通知:販売会社は年1回以上の通知が義務
トータルリターン=現在評価額+分配金累計+売却金額累計ー買付金額累計
▫️コスト
購入時手数料:購入時に販売会社に払う。同じ投資信託でも手数料は異なる。手数料なしもある(ノーロード)
運用管理費用:信託財産から日々引かれる。販売会社、委託者、受託者の業務費用
信託財産留保額:中途解約時に換金代金から引かれる。売却手数料の負担
外貨建て金融商品
▫️為替レート
TTS:円貨→外貨
TTB:外貨→円貨
TTM:基準レート(中値)
▫️商品
・外貨預金:外貨での預金
・外貨建てMMF:外貨での公社債投資信託。売買手数料なし。いつでも換金可能
デリバティブ取引
金融派生商品。
▫️先物取引
特定の商品を現時点で取り決めた条件で売買することを約束する取引。基本的には価格変動を避けるための手段。
▫️オプション取引
特定の商品を定められた期日に定められた価格で売買する権利の取引。
コール・オプション:買う権利
プット・オプション:売る権利
買い手(権利保有者):オプション料(プレミアム)を払う。権利の放棄か行使を選択可能
売り手(権利付与者):プレミアムを受け取る。売買する義務を負う
※満期までの期間が長い程、プレミアムは高くなる
※買い手は権利放棄により損失をプレミアムに限定できる
ポートフォリオ
ポートフォリオ:所有する資産、個別銘柄の組み合わせ
アセット・アロケーション:株式、債券、不動産等の資産配分
▫️相関係数
資産や銘柄の値動きの関係性。1だと値動きが同じ、-1だと値動きが全く逆となる。相関係数の低い資産や銘柄を組み合わせるとリスク低減効果が期待できる。
リスク:投資におけるリスクは通常値動きの大きさを指す
ボラティリティ(価格変動率)が高い → 高リスク
ボラティリティ(価格変動率)が低い → 低リスク
税金
▫️預貯金
利子は、利子所得として課税。20.135%の源泉分離課税。
▫️債券、株式、投資信託
口座の分類。
特定口座
- 源泉徴収あり:証券会社が計算して納税
- 源泉徴収なし:証券会社が計算。納税は投資家
一般口座:投資家が計算して納税
NISA口座:非課税
・債券
特定公社債(国債、地方債、公募社債等)
利子、収益分配金:利子所得として20.135%課税。申告分離課税(源泉徴収して申告不要にできる)
譲渡益、償還差益:譲渡所得として20.135%課税。申告分離課税
・株式
配当金:配当所得として20.135%課税。総合課税か申告分離課税(源泉徴収して申告不要にできる)を選択可能
売却益:譲渡所得として20.135%課税。申告分離課税
※総合課税の場合、配当控除が適用される
損益通算:譲渡所得で損失が出た場合、申告分離課税を選択した利子所得や配当所得と通算可能。損失は3年まで繰り越せる
・NISA
2024年1月に制度拡充。18歳以上が対象。非課税期間は無期限に。
つみたて投資枠:年間120万円。一定の投資信託のみ
成長投資枠:年間240万円。一定の株式等
非課税枠上限:1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)
※NISA口座は損益通算対象外
あとがき
興味のあるパートな分、知っていることも多いけど気になることも多く思ったより時間がかかりました…
投資全般の基礎知識を得るのに良い勉強になりました。曖昧な知識を補完できたり、自身が投資していないアセットの概要を把握できたり、一般投資家やこれから投資を始めようとしている人には結構おすすめの内容かもしれません。株式メインで取引している人は株式関連箇所の内容は薄く感じるとは思いますが。
今後の投資活動の参考になるかは何ともですが、このパートを通じて金融・経済に関する解像度は少し上がったかなと思います。やはり一度体系的に勉強するのは良いことですね。